赤ちゃんの夜泣きについて知りたい!いつからいつまで?原因と対策について
夜泣きがひどいと、ママもパパも寝不足になり、どんどんストレスが溜まってしまいます。
いつ終わりがくるのかわからない夜泣きと向き合うのはうんざりしてしまうかもしれませんが、夜泣きは成長の証でもあります。
赤ちゃんの夜泣きの原因や対策を知って、夜泣きを軽減できるようにしてみましょう。
悩み解決のためのヒントと、子育てがちょっと楽になるアドバイスをまとめました。
赤ちゃんの夜泣きとは

赤ちゃんは泣いて、さまざまな感情を訴えてきます。
言葉で自分の気持ちを伝えられないので、「甘えたい」「お腹が空いた」「オムツが不快」というように泣いている原因はひとつではありません。
夜に赤ちゃんが泣いて起きて、おっぱいやオムツ交換をしても泣き止まない場合もあります。
このように主に理由のわからないものを「夜泣き」といいます。
夜泣きはいつからいつまで?
赤ちゃんの夜泣きは一般的に生後5ヶ月~6ヶ月頃に始まる子が多いようです。
赤ちゃんの発達には個人差がありますし、性格や成長の過程も異なりますので、夜泣きがない子もいます。
生後5ヶ月~6ヶ月が目安にはなりますが、生後3ヶ月くらいでスタートする子も、生後1歳頃にスタートする子もいます。
さらに夜泣きが数日で終わる場合もあるし、数ヶ月継続する場合もあります。
夜泣きは記憶と認識の脳が発達する時期に起こりやすいともいわれていますので、発達のひとつの段階だと受け止め、上手に付き合っていきましょう。
赤ちゃんの夜泣きの原因について

赤ちゃんの夜泣きは、これらの原因が考えられます。
原因がひとつに限定されないケースもあり、ハッキリとした原因がわからないものもあります。
夜泣きの要素として捉え、当てはまるものがあれば改善できないか考えてみましょう。
- 生活リズムを作っている途中
- 日中の刺激が強い
- 体調不良によるもの
- 何か不快な原因がある
- 原因不明の夜泣き
私達大人は、朝起きて夜は眠るという当たり前のサイクルが出来上がっています。
しかし赤ちゃんは、まだ生活リズム(睡眠リズム)が確立されていません。
新生児期から成長をするにつれて、だんだんと夜はまとまった睡眠をとるようになってきますが、夜中に覚醒してしまう場合もあります。
赤ちゃんは睡眠の質が浅いといわれていますので、ちょっとした刺激で目が覚めやすいという特徴もあります。
睡眠のリズムも発達段階なので、成長とリズムができてくると夜泣きも自然となくなっていきます。
日中の刺激が強い
 赤ちゃんにとっては、全てのものが初めての経験であり、数分のお散歩でも脳ではたくさんの刺激を受けています。
赤ちゃんにとっては、全てのものが初めての経験であり、数分のお散歩でも脳ではたくさんの刺激を受けています。
光や風、人の話声や自動車の音など、大人では気にもしない物も刺激となります。
日中に刺激を受けすぎると、脳の処理が追い付かずに夜泣きの原因になる場合もあります。
ただしこの現象は赤ちゃんの脳が発達している証拠でもありますので、成長を見守っていきましょう。
赤ちゃんには適度な刺激を
日中の刺激に過敏になり避けすぎてしまうのは、赤ちゃんの発達にとって良い状況とはいえません。
夜ぐっすり眠るためには、日中の活動で刺激を受け、体力を使うのも大切です。
普段の活動範囲や赤ちゃんの体力、経験に合わせた活動を促すようにしていくといいでしょう。
生後1歳近くなると立って歩く子も増えてきますので、活動範囲が増えていくのは自然な流れです。
日中の適度な刺激とお昼寝時間の調節で、夜の睡眠を心地よいものにしてあげられるようにしましょう。
体調不良によるもの
赤ちゃんはママの免疫をもらって生まれてきますが、生後6ヶ月頃にその免疫もなくなっていきます。
風邪をもらいやすくなり、体調を崩しやすくなっていきますので、体調不良を訴えているというケースもあります。
「いつもの夜泣きと違う」と感じたら、体調不良も疑ってみましょう。
不思議なもので、ママの「なんとなく」という勘が的中するのも珍しくありません。
原因不明の夜泣き
一般的に赤ちゃんの夜泣きには上記のような要素が関わっていると考えられますが、原因不明の夜泣きもあります。
赤ちゃんの夜泣きの原因は、いまだ解明されていない部分も多く残されているのです。
赤ちゃんの夜泣きの対策
「日中の過ごし方もごく普通」「体調も悪くない」「ミルクもあげた」「オムツも清潔」という原因のわからない夜泣きの場合は、どう対応すればいいのかママも困ってしまいます。
成す術がなく途方に暮れてしまうかもしれませんが、夜泣きに困っている時は、これらの対策を試してみてください。
できるだけ夜泣きを起こさないための対策になりますので、できる項目からチャレンジしてみてください。
- 睡眠のルーティンを作る
- 環境を整える
- 生活リズムを整える
- 抱っこで触れあい安心感を与える
- 胎内に近い環境を作る
- 外気にあててみる
睡眠のルーティンを作る
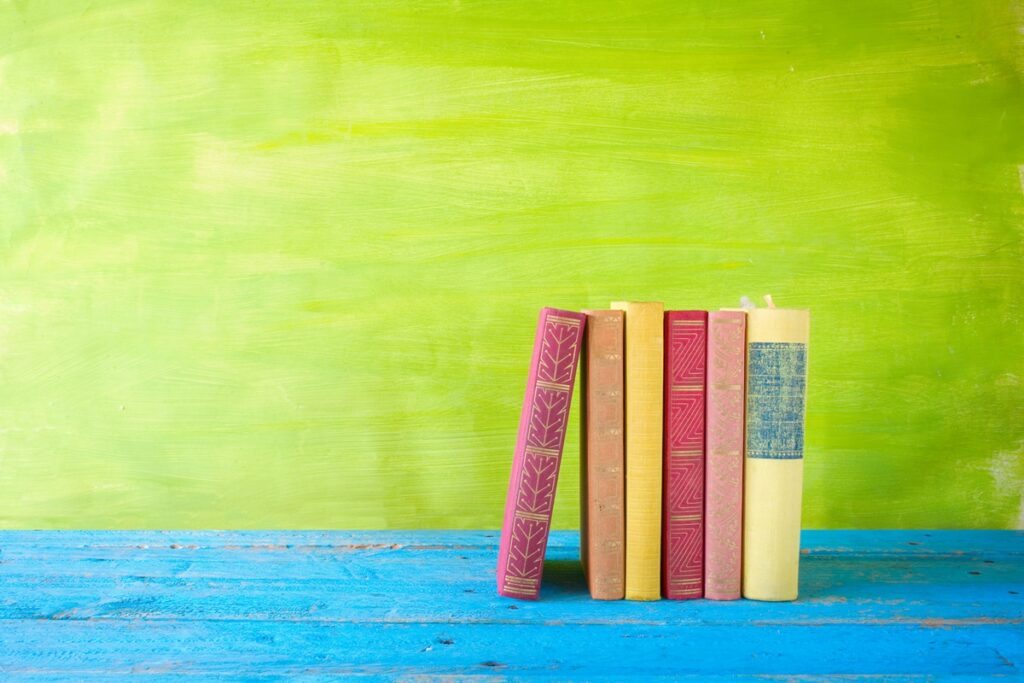
睡眠前に毎日同じように過ごすルーティンを作ると、赤ちゃんは「これから寝る時間」と認識できるようになります。
入眠儀式とも呼ばれ、毎日続けていくと寝付きがよくなり、夜起きる回数が減っていくといわれています。
具体的な睡眠ルーティンとしては、このような方法があります。
- 絵本を読む
- 歌を聞かせる
- お話をする
絵本を読む場合には、「最後は必ず同じ本にする」など決めておくと、赤ちゃんも終わりがわかってくるようになります。
楽しくなりすぎて目が覚めてしまうと逆効果なので、赤ちゃんのタイプや各家庭に合う方法を選んでください。
睡眠ルーティンのポイント
睡眠ルーティンを取り入れるのであれば、2つのポイントを意識してみてください。
- 毎日同じくらいの時間に取り入れる
- 一貫性を持って継続する
毎日同じ時間に睡眠ルーティンを行っていくと、赤ちゃんも同じくらいの時間に眠たくなるようになってきます。
一貫性を持って継続させていくと、ママ・パパ・じぃじ・ばぁばと人が変わっても、誰でもスムーズに寝かしつけができるようになっていきます。
睡眠ルーティンを行うと、赤ちゃんが安心して眠れる状態を作りだせるようになり、ぐっすり眠ってくれるようになるでしょう。
環境を整える
赤ちゃんが眠る部屋は、快適に眠れる環境が整っているでしょうか。
部屋の温度をエアコンで調節するのはもちろん、加湿器を使って湿度も調節してあげましょう。
- 夏場の温度目安26℃~28℃
- 冬場の温度目安20℃前後
- 湿度40~60%程度
季節によって温度の目安が異なりますが、室内外の温度差を5℃以内にできるよう意識しましょう。
湿度は40%を下回ると、ウイルスの活動が活発になり肌も乾燥してきます。
部屋の温度を調節するだけでなく、赤ちゃんの様子もチェックしてください。
汗をかいていたら涼しくし、手足が冷えていたら1枚毛布をかけてあげるといった細かな調節も大切です。
生活リズムを整える
赤ちゃんの生活(睡眠)リズムの未発達が、夜泣きの原因だとお伝えしました。
そのため生活リズムを整えていけるよう、大人も早寝早起きをしてサポートしていきましょう。
- 朝はカーテンを開けて朝日を浴びる
- 食事や入浴の時間は同じにする
- 昼寝の時間も同じにする
- 夜は部屋を暗くして眠りにつきやすくする
このような点を意識すると、生活リズムがつきやすくなるでしょう。
抱っこで触れあい安心感を与える

夜中に赤ちゃんの目が覚めても、「ゆらゆらと抱っこをしてあげたら自然に寝付いてくれた」という経験がある方も多いでしょう。
赤ちゃんはママとの抱っこで安心を感じますので、リラックスして眠ってくれます。
「早く寝てくれ~」という気もちで抱っこしていると、不思議と赤ちゃんに伝わり、なかなか眠ってくれません。
ミルクをあげたり、オムツを替えたりして不快感を払拭したら、ゆったりとした気持ちで抱っこをしてあげましょう。
胎内に近い環境を作る
ママのお腹の中にいた時と似た環境を作ると、赤ちゃんが安心して眠りやすくなる場合があります。
- 暗くて
- 静かで
- 温かい
赤ちゃんをおくるみで丸く包んであげるのも良いでしょう。
胎内に近い環境を作るのは「ディベロップメンタルケア」という産科のNICUでも取り上げられている、赤ちゃんが安心する方法のひとつです。(参照:高知医療センター)
外気にあててみる
夜泣きでどうしても困った時は、外気にあててみるのも方法のひとつです。
夜の風にふっとあたると、不思議と泣き止むという赤ちゃんも多いです。
抱っこ紐やベビーカーでお出かけをするのも気分転換になりますが、夜中だとハードルが高いと感じるママが多いでしょう。
ベランダに出たり、玄関の外に少し出るだけでも、赤ちゃんが泣き止む場合がありますので試してみてください。
夜泣きの放置はよくない
夜泣きは毎晩毎晩続く場合もあります。
ママも寝不足が続くと、夜泣きでイライラしてしまう日もあるでしょう。
何をしても夜泣きが収まらないと、「夜泣きを放っておきたい!」と思うかもしれません。
気持ちはわかりますが、夜泣きの放置はこれらの理由からあまりおすすめできません。
- 体調不良のサインをキャッチできない
- 赤ちゃんとの信頼関係が構築できない
体調不良のサインをキャッチできない

お伝えした通り、夜泣きは赤ちゃんの体調不良のサインの可能性があります。
赤ちゃんは「熱がある」と言葉で伝えられませんので、泣いて伝えようとしているかもしれません。
その夜泣きを放置してしまうと、体調不良に気付けないまま、赤ちゃんもママも辛い時間を過ごすことになりかねません。
- いつもよりぐったりしていないか
- 鼻は詰まっていないか
- 体温が上がってきてはいないか
- 発疹が出ていないか
このような体調不良のサインをキャッチしたら、様子をみて小児科を受診しましょう。
赤ちゃんとの信頼関係が構築できない
赤ちゃんとの信頼関係は、毎日の生活の中で築かれていきます。
「泣いて自己主張をしても、誰も来てくれない」とわかると、赤ちゃんは不安になってしまいます。
夜泣きが全然ないという赤ちゃんの話を聞くと、羨ましく感じるでしょう。
しかし、サイレントベビーという反応のない赤ちゃんだと、それはそれで心配な要素になりかねません。
夜泣きは正常な発達のひとつでもありますので、あまり抱え込まずに成長を見守りましょう。
夜泣きとの上手な向き合い方
夜泣きが続くと、ママの気持ちも体力もすり減ってしまいます。
赤ちゃんの夜泣きは、明日終わるかもしれませんし、これから数ヶ月続くかもしれません。
上手に赤ちゃんの夜泣きと付き合っていけるよう、これらのポイントを覚えておきましょう。
- パートナーと協力する
- 寝れる時に眠っておく
- 気分転換をしてストレスを溜めない
- ご近所に挨拶をしておく
- 助産師さんなどに相談する
パートナーと協力する
毎日の夜泣きを1人でみていては、精神的にも体力的にも大変です。
パートナーや家族の理解・協力は必要不可欠となりますので、話合って分担を決めてもいいでしょう。
パートナーに協力してもらうと、負担が分散できるだけでなく、自分事として大変さも理解してもらえるようになります。
寝れる時に眠っておく

夜泣きに付き合っていると、何時間も眠れないという日もあるでしょう。
「赤ちゃんが昼寝をしているタイミングで大人の用事を済ませたい」と考えるかもしれませんが、まずはママも眠りましょう。
寝れる時に眠るという意識を持って、休む時間を作るのが大切です。
気分転換をしてストレスを溜めない
夜泣きに付き合っていると、寝不足になり、疲弊し、心に余裕がなくなっていきます。
「赤ちゃんとは笑顔で接したい」「良いママでいたい」と思うと、ついつい頑張りすぎてしまいます。
赤ちゃんと笑顔で過ごすためにも、気分転換の時間を大切にしてください。
ご近所に挨拶をしておく
赤ちゃんの夜泣きの声が大きくて、近所迷惑が気になるというママもいるでしょう。
挨拶に行くとお相手がどんな方かわかりますし、「こちらが気を使っている」と理解してもらっておくだけで相手の気持ちも優しくなるはずです。
赤ちゃんが夜泣きをする際の心配がひとつ消化されますので、事前に挨拶をしておくのもいいでしょう。
助産師さんなどに相談する
家族やパートナーなど身近な人に協力をしてもらうのも重要ですが、ストレスが溜まってしまったら地域の保健師さんや助産師さんに相談をしてみましょう。
地域の保健師さんは役所で相談をすれば窓口を紹介してもらえるでしょうし、近くのスーパーで助産師さんの相談会が開催される場合もあります。
大きな悩みではないかもしれませんが、少し話を聞いてもらうだけでも心が軽くなりますし、意外なところからアドバイスをもらえるかもしれません。
保健師さんや助産師さんを頼って子育てを
赤ちゃんの夜泣きは、生後5ヶ月~6ヶ月頃に始まる子が多いです。
初めての子育てだと、まだまだママも新米で、日々成長する赤ちゃんのお世話に慣れない日々を送っているでしょう。
夜泣きは脳の発達の過程で起きるという考え方もあり、正常な成長段階のひとつと考えられます。
息抜きやストレス発散をしながら、赤ちゃんの夜泣きと付き合っていきましょう。
この記事を書いた人
メルシーママン編集部
育児に関するお役立ち情報やママさんたちが感じているお悩みを解決できるような情報を発信します!

